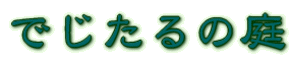
| このページでは、各種D/Aコンバーターの製作を扱います。正直、デジタル関連の知識が疎く、雑誌で発表された事柄の追試程度のものしか扱えないと思いますが、何かのご参考になれば幸いです。 |
 ソフトン Model 2 |
| First update 04/07/20 Last update 05/03/31 |
| ソフトン真空管式DAコンバータ Model 2の基板を使って、筐体を手持ちのもので活用したDAコンバーターです。 Model 2に関しては、雑誌で幾度も紹介されたり、現在ではサンバレーからもキットが発売されていたりしておりますので詳細は省きますが、真空管を使ったDAコンバーターとしてもっとも廉価な現行品として高い人気を持つ商品です。設計者の善本(sy)さんが95年頃にNiftyにて発表した真空管DAコンバーターの2代目として98年にNiftyで発表され、基板と主要部品のセットが希望者に実費で頒布されました。今回の製作物は、当時入手したものの暇がなくなってお蔵入りにしていた基板を、真空管アンプが趣味の叔父が興味を持ち「音を聴いてみたい」と言い出したのをきっかけに、重い腰を上げたものです。 製作するにあたって音質傾向をネットや雑誌紹介で検索すると、真空管の良さを感じさせる滑らかさといったポジティブな評価のほかに、音の厚みが少ない、低音が弱い、音像重視で音場感が希薄、といったネガティブな情報も入ってきます。それらを踏まえて使用部品の吟味を行いました。 基板の特徴としましては、コンパクトに比較的高密度な実装で、主要部品が殆ど基板上に載る設計で、筐体周りの組み立て工程が簡素化される良い設計ですが、小型の基板に部品が集積されている関係で、大型のオーディオ用ケミコンが使いにくいです。よってデジタル部の小型のケミコンはニチコンの汎用品(画像では緑ミューズと区別がつかないのですが)、高圧部・ヒーター部のケミコンはニッケミの汎用SMGを使い、様子を見ます。小型のコンデンサーで定番なのはOSコンですが、今回は叔父の音の好み(厚みがあり、艶のある音が好き)や、以前製作したDAコンバーター使ったOSコンで、音を生かしきれなかった(高域の癖が抜けなかった)経験から、今回は避けました。同じ理由で、デジタルICのデカップリング用途の積層セラミックコンデンサーは、音質に関係する部分には避けて、小型のフイルムコンとしました。デジタルのデカップリングでケミコン+小型フイルムを使うのは、ソニーをはじめとしたメーカーの中級製品ではよく行われる手法ですね。DACのPCM-1716のデカップリングのケミコンも本当は銘柄によって音が左右されるので微妙なのですが、まずは汎用の音を聴いてみます。 抵抗の選択も重要で、艶+クリアさならデールの無誘導巻線、艶+柔らかさ重視で選ぶとすると、リケノーム、東京高音RD、アーレンブラッドレー、といった大型カーボン抵抗に限られるようですが、ここは敢えて福島双羽のスケルトン抵抗を選択しました。これは金田式との相性も考慮した感じですが、まずは色づけの極力少ないと思われる抵抗で試聴したかった事、見通しの良いリアルな音場が期待できる事、オリジナルのModel2か酸金の抵抗をメインに使っている事から、同じ酸金の一種であるスケルトンで試してみよう、と思ったものです。酸金抵抗は概してオーディオ的な説得力に欠け、電源等の容量が必要な場所にしか使われない傾向がありますが、大抵素直でニュートラルな音がするので、他のパーツとの併用で、音質を生かしたいものです。但し、DAC直後のフィルター部に大型抵抗を使うと、音色は良くても音場の見通しが甘くなる経験があり、若松で売っているミニスケルトンを使う事にしました。1/2Wのサイズですが、塗装が無いと本当に小さな抵抗です。 出力のカップリングコンデンサーのクオリティは、音場の広さやクオリティと関係するので、良いものを使いたいのですが、容量が10uFに達するため、なかなか手が出ません。双信V2Aも手持ちを組み合わせれば可能ですが、ちょっと大きすぎて難があります。ここは妥協して安くて音にキレがあり、素性がよく判っている日立MTBにしました。秋葉でよく入手出来る黄色いコンデンサーの中では、唯一私が気に入ったものです。ASC等の高いCと比べると高域があばれますが、情報量はなかなかのものです。LPF部のCにはディップマイカを。ここは耐圧の関係もあり、あまり選択肢がありません。 ・・・と、ここまで部品を選択してきて、最初の目論見「厚み・艶・柔らかさ」を持った部品が殆ど含まれていない事に気が付きました。大丈夫かいな?? とりあえず抵抗以外はオリジナルと同等という事で比較対象し易いと考える事にします。 |
▲TOP ●HOME |
| 容量の大幅倍増を考えてみたものの、フイルムコンはとても入りそうにありません。そこで、フイルムコンを諦め、手持ちにあったブラックゲートVK
160V47uFを使ってみました。±2電源でもないアンプの出力カップリングにここまで大きな容量のものを使うと、普通はON
OFF時のひどいオフセットで使い物にならないアンプが出来上がってしまうのですが、このDAは保護リレーがOFF時に出力をショートしつつ、560Ωの抵抗を介してカップリングのディスチャージをしますので、安全に使用する事が出来ます。 取り替えて試聴してみますと今までの評価一変、手持ちのCDプレーヤー群と比べても遜色ない音場の広さ+音の厚みが得られてかなり満足となりました(^^)v。音の厚みと濃い目の音色がソースによらず似たような感じになるとか、ケミコンだからなのか音像がちょっとソフトフォーカスに感じる、音場の精度に欠ける印象がある、等の欠点もあることはあるのですが、トータルでの印象はBGMとして長時間リスニングする用途としてはとても良好で、スワン等の敏感なSPに繋がなければ、欠点はあまり気になりません。 あと面白い特徴として、トランスポートの差が良く出るようになった、という感じがします。手持ちの現用機はCD-10とCD-816なのですが、共通のメカ部とほぼ同様の回路構成ながら、電源と筐体の違いにより、シャープで力強い中高域なCD-10と、音に柔らかさといった要素が出ている改造CD-816ですが、その傾向が良く出て、バランス良いCD-816改+Model2に対して、少しシャープな感じの音がするCD-10+Model2といった風になりました。最初あまり良さが判らなかったデジタルインターフェイス部の改造の効果でしょうか? ここの製作をする前には気がつかなかった効果ですし、ブラシーボと思いたくないなぁ(^^;; まぁ、エージングに時間のかかるといわれるBGですからしばらく鳴らしつつ、癖が残るようでしたら、パラにするフイルムコンを見繕うとしましょう。最後に抵抗をRMAとRMGの混成に全て取り替えてみました。変化度はカップリングのBG程の大きさではないものの、BGの音の厚みに艶が載った感じで、相性も良く馴染みます。よく癖の事が言われる抵抗ですが、評判どおり叔父が好む女性ボーカルやバイオリン等では、持ち味をフルに発揮するようです。さすが球アンプに良く好まれる抵抗ですね。今回使ったBGの音質を考えると、+B電源回路部にも多用したくなりますが、残念ながら基板の余白の少なさがそれを許しません。手持ちにはこのDACの設計母体となったModel1も手持ちにある事ですので、いずれそちらで試してみる事にしましょう。何か白金田式?をいじる時の慎重な定数吟味とはかけ離れた(^^;; アバウトな音質チューニングですが、久々に楽しめた工作になりました。あとは叔父の判断一つですが、さてさて? (05/03/31 了 ) |
▲TOP ●HOME |